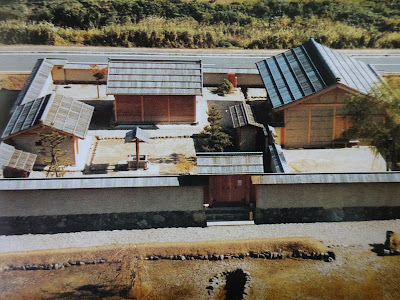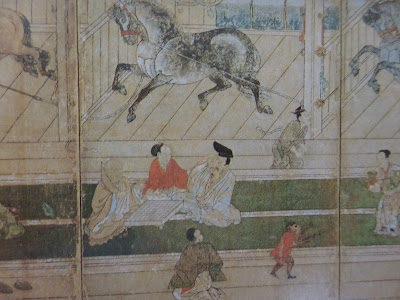1677(延宝5)年に、現在の小立野1丁目付近に聞敬坊として創建された。1821(文政4)年にな七カ町村の惣道場として現在地に建てられ、1880(明治13)年に「聞敬寺」となった。

本堂の障子の隙間から見えた、金一色塗りの宝相華花草文様が見事な内陣の欄間は、200年以上の欄間様式であるという。
本堂の前にクロマツの立派な木があるが、高さ18m、幹周り2.9m、枝幅16mで金沢市指定の保存樹となっている。小立野台地のこの辺りの貴重な緑であるという。
静かな住宅街にちょっと奇抜なや建物があった。大戸があり、ガラス格子戸の枠や2階の手摺などが紅殻色だった。
後で通った時に店の前が開かれていて、きれいな和傘や桐工芸の火鉢など金沢の伝統工芸品が並べられていた。また、鴨居の上に家紋が描かれた箱が並べられていたので古い町屋なのだろう。現在は何の店なのかよくわからなかった。
そのすぐそばには店先に野菜や果物が並べられ、この辺りの便利な小さなマーケットである「ひまわりチェーン」があった。
さらに歩いていくと「善光寺坂」の標柱があり「昔この付近に善光寺という寺があったのでこの名で呼ばれている。」とあった。
この坂の下り口の右側に大きな地蔵堂がある。
窓から中をのぞくと、大変大きな顔の地蔵さんが、目を細めて笑っているような、祈っているような心優しそうな顔をしている。幕には梅鉢紋が描かれている。
この「善光寺坂」は、どこに善光寺があったかは分からないという何の変哲もない坂で、斜度は3度から4度で長さが300mというなだらかな坂である。また、緩やかに曲がっているので先が見えない。
坂の途中に別に下りる道が何本かあるようだが、この先は個人の家に行くのかよくわからない。この下側には「大清水」という湧き水が出ている方向に行くはずだ。
この後、ランチをとるために「マルエー小立野店」の向かいにある洋食の店「グリルニュー狸」に入った。

私は初めての店だが店内は結構混んでいて、近辺では有名な店らしい。ハンバーグとカキフライと野菜サラダが出てきたが、おいしかった。